冷たい雨の音の中に夏の始まりを予感させる陽射しが差す頃、皆様如何お過ごしでしょうか。お久しぶりです。実に一年ぶりのブログ更新をするジェムでございます。前回の更新が去年の6月と知り仰天する5月の幕開けです。
さていきなりですが、5月の第2日曜日は母の日ということで、ディズニープラスでは「母の日特集」として「母と子の愛情」を描いた作品がラインナップされました。
が、その中でまさかの継母ヴィランの代表格である『塔の上のラプンツェル』が華やかにメンバー入りを果たしたらしく、相変わらずのWDJの詰めの甘さを感じてしまう運びとなりまして。
そんな「オタクにすら呆れられがち」でお馴染みウォルトディズニージャパンですが、今回私は担当の方にぜひ感謝を述べたいくらい、正直言ってラプンツェルなんか(と言ってはファンに怒られそうですが)よりも何よりも、ラインナップされていることが嬉しかった作品が存在します。
何を隠そう、『ルイスと未来泥棒』がその作品です。
あらすじ
親に捨てられ孤児院で育った発明好きのルイスは、124回目の里親受け入れ拒否をされていた。もう自分を受け入れてくれる人は居ないと悟った彼は「実の母親だけが自分を愛してくれる」と考え、母親を探して、もう一度2人で一緒に暮らそうと考える。そんな彼の元に未来から来たウィルバーという少年や、ウィルバーの家族たちが現れて….。
1990年発売の「ウィルバーロビンソンの1日」という本を元にしていますが、ストーリー自体は殆どWDASのオリジナルとなっています。
.
2007年公開の本作品は、実は初めて3Dのシンデレラ城のオープニングが用いられた作品でもあります。「蒸気船ウィリー」のワンシーンより、ミッキーが口笛を吹きながら船を操縦するロゴクレジットも本作で初めて使用され、以降全ての作品で使われるようになりました。
そして本作品はウォルト・ディズニー・フィーチャー・アニメーションが現在のウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ(WDAS)に変更されてから、記念すべき一作目の作品でもあります。
何故ここまでスタジオの改革が行われたのか? というのも、この作品は実はディズニー社がピクサーを本格的に買収して以降 "初" の、WDAS長編映画となっているからなのです。
ピクサーとのハッキリとした差別化のために社名変更が行われ、CCOに任命されたラセターによる「クリエイター主導」の映画づくりにシフトチェンジしていった、言わば「第三次黄金黎明期」の作品とも言えるでしょう。
作品の内容もストーリーの構成や見事な伏線回収、そして一貫したテーマである「未来は自分で作るもの」というメッセージなど、ディズニーの新時代を思わせる素晴らしい出来となっています。
未来への手引き
本作品は、ウォルトの残した
"Around here, however, we don’t look backwards for very long.
We keep moving forward,
opening up new doors and doing new things,
because we’re curious…
and curiosity keeps leading us down new paths. "
(長い間、後ろは振り返らずにやってきた。
前進し続け、新しい扉を開けて新しいことをした。
なぜなら私達は好奇心に溢れていて…
好奇心こそが私たちを新しい未来へ導いてくれるからだ)
という言葉に非常に強いインスピレーションを受けており、映画の最後のシーンではこの言葉がそのまま引用されています。
ストーリー自体もこの言葉を解釈してできたような展開で、例えば主人公のルイスは映画内で何度も何度も発明品を作りますが、その大半は失敗に終わります。
しかし、ルイスの失敗を見たウィルバーやロビンソン一家はあえて失敗を「褒め」るんです。「失敗したぞ!おめでとう!イェーイ!」といった具合に。
お祭り騒ぎのような雰囲気、極めつけには「Keep moving forward!(前進しよう!)」と書かれた横断幕や花火まで出てきちゃったりする。
何故ロビンソン家は失敗を褒めるのか? 家族たちは口々にこう答えるんです。
「失敗からは成功よりも多くのことを学べる」と。
過去を"水に流す"ディズニー
さて、1923年にWDASが創立して以降、現在までにスタジオは知らない人は居ない程大きくなり、沢山の名作を生み出してきました。
しかし最近では、過去に発表された作品について「人種差別的ではないか」「男尊女卑的てはないか」という批判が多く見受けられます。以前ブログでも紹介した通り、過去の作品に疑問の残る描写が少なからず存在することは確かです。
ディズニー作品の配信に特化したストリーミングサービス・ディズニープラスでは該当するシーンが削除されていたり、そもそも作品の配信自体が無くなったりという対応が為されています。
ところで先日、『ラーヤと龍の王国』が公開された後に「EDにある"水に流す"という表現は歴史修正主義的で、社会を"綺麗に元通りにする"という理想論は綺麗事臭い」といった旨のツイートを拝見しました。
さて、先程本作は「今まで悪役とされがちだった”継母”に居場所を与える魔法」と評しましたが、本作の中でもう1人、「居場所を与えられた人間」が存在します。
しかし、『ルイスと未来泥棒』という作品をもう一度しっかり観てから考えると、WDASに対するこういった批判は間違いであることがわかります。
WDASの(少なくとも、本作品の)「過去を忘れよう」というのは、決してネガティヴな文脈で使われているものじゃないんですよね。「過去の失敗にくよくよしていないで、失敗から得られるものを大切にしよう」という前向きな意味でしかないんですよ。
ディズニープラスにおける配信停止は私自身未だに賛成はできないのですが、WDASが前述のように多くの批判を受けている2021年現在に「put the past behind 」という言葉の存在する作品を配信することの意義については、もっと深く考える余地があると思いました。過去は過去、それはそうとして、大切なのはやはり未来なのです。
ディズニーの打ち出す「家族像」について
さて、先述した「ディズニーに対する批判」というもののうちひとつに、「ディズニーは"血縁依存"的である」という批判が存在します。
簡単に説明すると、「ディズニー映画の多くは"継母が悪役"であり、結局血の繋がった家族の元に帰ってくるストーリー展開など、"血縁こそ家族の絆である"と思わせる作品が多い」といった批判です。時に「家族の呪い」「血縁の呪い」などと称されるそれです。
過去にTwitterで取ったアンケートでも、約70%の方が「ディズニー映画は血のつながりを大事にしがちだとかなり思う・まぁそう思う」に投票しており、「ディズニー=幸せな"血の繋がった"家族像を描く」という認識を多くの方がされていることがわかります。
ディズニー映画、血の繋がりを大事にしがち?
— 𝙂𝙀𝙈𝘼𝙍𝘼 (ジェム) (@Gemararara) October 28, 2020
確かに、現実に目を向けてみると、血の繋がった家族であっても虐待に及ぶ家庭や決して幸せではない家族というのも存在し、「"血縁家族"が礼賛されること」について、疑問を持つ方も居るかもしれません。
しかし、私はそんな疑問を持つ方にこそ、『ルイスと未来泥棒』という作品を観て欲しいと思うのです。
実は、本作の監督を務めたスティーブン・アンダーソン氏は実際に幼少期に養子縁組をされた「血縁でない家族」で育っており、母親の顔を知らなかったそうです。
幼少期のアンダーソン監督
アンダーソン監督は幼い頃、「自分はどこから来たのか?」「母親は誰で、どうして自分を育てられなかったのか」といった疑問を常に持っていました。映画内のルイスと全く同じ心境であったと彼は語ります。
監督の義両親はこの事について寛容で、「18になったら自分の本当の母親を探してもいい」と仰ったそうです。子供だったスティーブン監督は言われるがままに「18になったら本当の両親を探して、もう一度その人達と家族になろう」と考えていましたが、ある日気付きました。
「自分はもう24だ。本当の親を探して過去を知ったところで、それで何になるんだ?」と。
.
「捜そうと思えばいつでもできたのに、その時には両親を探すなんてことはすっかり忘れていた。過去に何があっても関係ない。大切なのは過去ではなく、自分自身の将来だということに気付いたからだ。」
.
(ここからは本編のネタバレを含みますので、先に視聴しておくことをお勧めします)
さて、『ルイスと未来泥棒』という映画の名シーンをひとつ挙げるとするならば、私は迷う事なく最後の「主人公ルイスがタイムマシンで自分が捨てられた日に戻るシーン」と答えます。何度本作を観ても、このシーンだけは涙なしには観られないからです。
ルイスの当初の目的であった「本当の母親の元に戻り、自分を家族にしてもらいたい」という願いが叶うはずのシーンですが、ルイスは自分の母親が愛おしそうに自分を抱きしめるのを見たあと、あと少し、というところまで母親に伸ばした手を引っ込め、そして彼は静かに、音を立てないようにそっと後ずさります。
その後ウィルバーが「どうして話しかけなかったんだ?」と尋ねると、ルイスは笑顔でこう答えるのです。
「僕にはもう家族がいるから」と。
.
ウォルト・ディズニーの幼少期
さて、スティーブン監督の生い立ちが分かっていただけたところで、本作の重要なインスピレーション元であるウォルト・ディズニーという存在に目を向けてみます。
ウォルトはフランスのノルマンディーからイギリスに渡った一家の子孫で、ウォルトの父イライアスがアメリカに渡ったのちに生まれたいわゆる「移民二世」に当たります。治安の悪い移民街からミズーリ州に引っ越しますが、暮らし向きは決して良くありませんでした。
加えて彼の父は厳格で、娯楽は禁じられ、小学生のうちから父親の新聞配達の仕事を手伝わされ起床は3時、うとうとしながら学校に向かう生活の繰り返しでした。恐ろしいことにこの時の「担当区域のどこかに新聞を配達しわすれたのではないか」という不安は、彼を晩年まで苦しめ続ける程だったそうです。
ウォルトの上の兄2人は、そんな父親の権威主義に耐えきれず既に家を出ていってしまった後でした。
何が言いたいかというと、ウォルト・ディズニーという男は、決して「幸せな血縁家族」の中には居なかったのです。
しかし、それでもウォルトは現在「家族の呪い」と揶揄されるような作品や、『レディアンドトランプ(1955)』のような「幸せな家族像を目指す」作品を作り続け、ディズニーランドという名の「家族で楽しめる場所」の建設に情熱を燃やし、「前進し続け(keep moving forward)」てきました。
ウォルト・ディズニーという男は、自身が決して幸せにない家庭にいた中で、それでも「家族の大切さ」、つまり「幸せな家族像」を表現し続けた人間なんですよ。
彼は確かに「家族像を礼賛」する作品を多く作りました。ですがそれは「血統こそ正義である」とかそういった次元の話ではありません。血筋などは関係なく、とにかく「家族とは素晴らしいものである」ということを説いた「家族像の礼賛」な訳です。WDASという会社が「家族とは暖かく、素晴らしいもの」という作品を作り続けることにはちゃんとした意味があるのです。
ちなみに、ウォルトは生前のミッキーの短編等でいくつか「養子」についての作品も制作しており、(例えば、『Orphan's Benefit(ミッキーの芝居見物)』では、ミッキーを始めとしたキャラクター達が孤児のために無料のショーを開催するといった内容になっている)
作品の内容を鑑みても決して「血縁至上主義」という訳ではないといえます。
.
加えて、本作品では「養子縁組adoption」という言葉がキーワードになっています。
振り返ってみると、確かに本作の公開以前では『白雪姫』の継母や『シンデレラ』のトレメイン夫人など、過去の童話からそのまま設定を持ってきた作品で陥りがちな「継母は悪い人である」という描き方しか出来ていなかったのは事実です。しかし前述したようにウォルトの「家族像の礼賛」は、「血筋こそ正義である」の思想とは全く異なります。このままでは間違った印象を観客やファンに植え付けかねません。
という訳で、本作ではルイスが「養子として育てられ、幸せな家族像を築く」という展開が採用されました。
これは今まで悪役とされてきた「継母」という存在に居場所を与える魔法でもあり、WDASが目指す家族像が決して「血筋家族」に限定したものではないことの証明でもあります。
ウォルト・ディズニー、ルイス、そして本作の監督であるスティーブン・アンダーソン氏という3人の「家族」に関する経験は、『ルイスと未来泥棒』という作品にてひとつに「結合adapt」したということです。 こんななところでセンスのない親父ギャグみたいなまとめ方をしてしまってすまん。
.
(閑話)
時にWDASは、ピクサーなどの他スタジオと比較され価値を貶められたり、大手であるが故に表現が縛られ何もできないと思っている方が一定数存在したりしますが、いわゆる「あまり売れなかった作品」が多かった時期、暗黒期と言われる作品を見てみると、アンチヒーロー的で「剣のことを知らない女の子のおかげで貴方は助かったのよ!」と言ってのけるエロウィー姫が登場する『コルドロン』や、脱ヴィラン的なストーリーの『トレジャープラネット』、そして今回紹介した、義理家族を描いた『ルイスと未来泥棒』など、野心的な作品が多く存在していることは否めません。
そして、それらの作品に目を向けず、売れた作品やプリンセス作品ばかりを帰納法で判断し「ディズニー作品はこうだからダメだ」と言ってしまうのは、非常に暴力的なことだと私は思います。
(閑話休題)
"誰も傷付けない”の真骨頂
本作のヴィランのうちの1人、「山高帽の男Bowler Hat Guy」ことマイケル・”グーブ”・ヤグービアンです。
まさかの監督本人が声を当てているとは、観ている皆さんは気付かなかったんじゃないでしょうか? 私は気付きませんでした。
グーブはルイスと同じ孤児院で育ったルイスのルームメイトかつ親友でしたが、ルイスの記憶スキャナー開発が深夜まで及んだために寝不足を発症し、肝心な試合の9回裏の居眠りで捕球ミスをしてしまいチームから大ブーイングを受け、里親候補も見つけることができず、以降ルイスを恨む事になります。
山高帽の男は映画の中盤で幼少期の自分(グーブ)と出逢いますが、そこで幼少期のグーブは「先生はもう”忘れろ(let it go)”って、だから忘れるよ」と言いますが、そんな幼少期の自分を見て目を潤ませた山高帽の男は「ダメだ!みんなが”忘れろ(let it go)”というが絶対にダメだ、DON’T LET IT GO(恨みを忘れるな)」と彼に教えます。
……あれ?どこかで聞いたことあるぞ?
姐さん...........!
グーブは山高帽の男に言われた通り恨みを忘れずに、過去に囚われたままルイスへの執念を燃やします。しかし終盤で自分のしていた行為が間違いであったと気付き、ルイスとウィルバーの前から寂しげに姿を消してしまうのです。
今までの「反省することなくブチ死ぬヴィラン」と比べると彼は異色であり、近代ディズニーで多く見られる「ヴィランも私たちと同じ人間」といった展開の先駆者であることがわかります。
でも、『ルイスと未来泥棒』の凄いところはこれだけには留まりません。
ルイスは現在に戻った後、急いで野球場に向かいグーブを起こします。
グーブは捕球に成功、チームのヒーローとなり優勝カップを持ち帰ることとなります。彼はなんと里親まで見つけることができました。
ただヴィランに反省させるだけではなく、タイムマシンという本作のキーアイテムを使ってヴィランの過去ごと「救って」しまったんですよ。
そしてその後に流れるエンディングの歌い出しは、"Let it go(前へ進もう)"となるんですね。
映画全体のkeep moving forwardというメッセージを体現したのは主人公ルイスだけでなくヴィランズのグーブもである、というのはWDASでも珍しいキャラクターの配置です。
更に彼は映画の冒頭からずっと登場するキャラなため、観客に違和感や蟠りをそこまで感じさせることなく、スッとグーブの側にも感情移入することを可能にしています。これはラセターの技巧的なストーリテリングにおける最高傑作と言っても過言ではないんじゃないでしょうか?
まとめ
今回は『ルイスと未来泥棒』について、「家族像」「ヴィラン」という二つの観点から私の好きなポイントを語らせていただきましたが、正直本作を観た方なら絶対にわかるであろう「ここが好き!」ポイントについてまだまだ語り足りないところが多くあります。あるでしょ?カエルのあれとか、個性あふれるウィルバー家の良さとかさぁ…?みんなも一度は「ウィルバー家の養子になりたい」って思ったでしょ…?
とにかく、かなりの文字数で解説したにも関わらずまだまだ言及しきれないほどに「良さしかない」作品なので、もしこのブログを読んで観たよ!という方がいたらそれはもう嬉しすぎて圧死します。(?)
ちなみに導入部で少しお話したWDJですが、ルイスと未来泥棒のポスターでは「本当に発明したかったのは、《家族》かもしれない_____。」という非常に興味深いキャッチコピーをつけていらっしゃいます。
そんなこと言ってるうちに皆さんも観たくなってきたんじゃないでしょうか。
今夜はリビングの明かりを消して、未来の自分に思いを馳せようか。


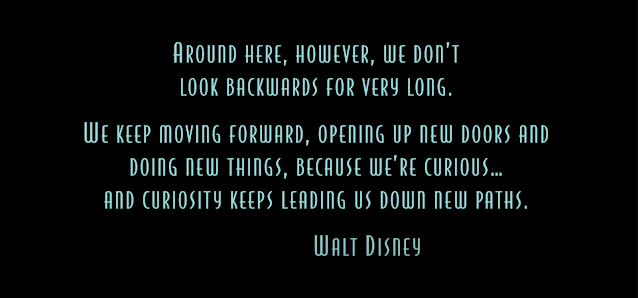








0 件のコメント:
コメントを投稿